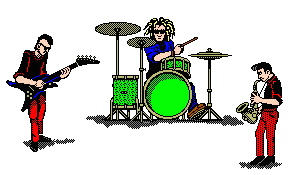恐怖のラオ・ダンス
別に自慢するわけではないのだが、私はラオスのサワナケートという田舎町で一週間も沈没してしまった、という輝かしい記録を持っている。ラオスのことを少しでも知っている人なら、これがどれほどの偉業か、分かっていただけるのではないかと思う。
サワナケートはラオスの他の都市のご多分にもれず、正直言ってえらく閑散とした所だ。道路はもちろん舗装されておらず、砂ぼこりが美しく舞い、見所もたいして無く、旅行人ノートには「見るべきものは夕暮れ時のメコン川くらい」とある処である。こんな町になんで一週間近くものびていたかと言うと、それはただ単に「この街から脱出する手段がなかった」という事につきるのだ。
よく知られるように、ラオスには快適で便利な交通機関がなかなかない。ポピュラーなのがトラックの荷台そのもの、ちょっと高級になると荷台のうえに幌がついて雨風を防いでくれるのだが、恐るべきことにこれらの公共交通機関は、しばしばとんでもない時間に発車するのだ。なんと朝五時、六時というのが当たり前の世界で、これでは早起きが苦手で、朝は寝過ごすのを信条としている人は永遠にバスに乗れない。サワナケートの近くには「コーンの滝」などの観光地があるのだが、わざわざ朝五時に起きて滝を見に行く気にはどうしてもならず、必然的にサワナケート脱出に失敗してサワナケート沈没の道を歩み始めたのだ。
だが、今では私の逃亡計画を失敗に終わらせてくれたラオスの交通機関と悪路に、感謝している。サワナケートからの脱出に成功していれば、私はあの奇怪な「ラオ・ダンス」を踊ることもなかったであろうからだ。
サワナケートは前述のようにメコンに沈む夕日だけが美しいひなびた街だが、なぜか「ディスコ」だけはあった。暇を持て余した私は夜な夜な踊りに行った。そこは日本のものとは少し違って、半分ナイトクラブ、半分ディスコのような処だったけど、そこで繰り広げられていた奇怪なダンスがここでは問題なのだ。
それはもちろん、日本のような踊りではない。一人欧米人が本国と勘違いして派手なダンスを披露していたが、完全に浮きまくっていた。ここではそんな慎みのなさは通用しない。
まず、舞台に上がる。ラオ・ダンスは集団で踊るのである。たて三人、よこ五人ぐらいになって整列する。この整列するあたりに、何かアジアの奥深さを感じる。
音楽が始まる。レコード、CDなどという無粋なものと違って、豪華生バンドであることが多い。
ラオ・ダンスでは、手足をあまり動かさない。体もそれほど動かさない。ただ、曲が進行している間、ぽつねんと立ち尽くす。だが単につっ立っているだけではだめで、「私はいま踊っているのですよ」という意志を見せなければだめだ。さりげなく音楽に合わせて体を揺する。人は列になって、みな同じ方向を見ている。
だが、その時、恐るべき転換が始まる。曲のある部分にくると、みんな一斉に体を九十度回転させ始めるのだ。集団全体が九十度横に向いた感覚になる。たいていの人はこのタイミングが掴めずに驚くだろう。私もきっちり、間違った。どうやら、「この曲のこの部分で体を回転させる」ということは決まっているようなのだ。
しばらくこの繰り返し。曲のある箇所にくると九十度回転させ、またある箇所にくると九十度回転する。このあたりにくると「何だ、簡単じゃないか。ようするに延々と回転し続ければいいんだ」と早合点してしまう人もいるだろう。
だが、ラオ・ダンスはそんなに甘くないのである。気を抜いていると、えらい目にあう。ある箇所にくると、人は体を回転させながら無茶苦茶な蛸踊りを始めるのだ。これもたいていの初心者にはタイミングが掴めない。だが、ほかのラオス人は一糸乱れずに踊っているので、ここには何か分からない神秘の法則が介在しているようである。私も真似して踊る。これの繰り返し---
踊りながら、私は、「ラオスの魂」を見たような気がした。何の役にも立たない旅だけど、わざわざ日本から来て、ラオ・ダンス踊っているような人もそんなにいないだろう。そう思うと、無益な旅ながらなんだか得したような気になったものである。
(『旅行人』2000年8月号掲載)